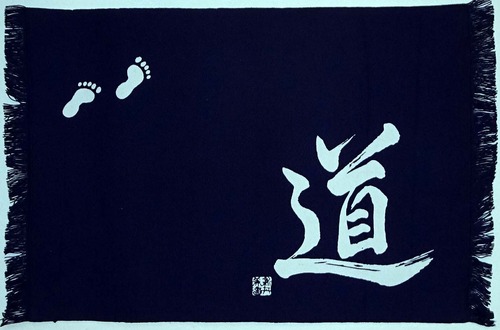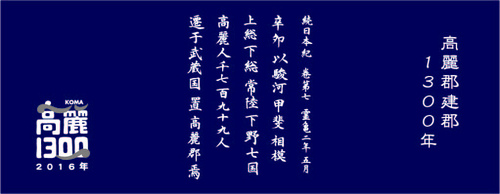川越市今成町囃子連様より浴衣のご注文をいただきました。
川越市今成町囃子連様より浴衣のご注文をいただきました。
角字で今成囃子連という文字が全体に配置され(総柄)の絵羽という染めです。
17日、川越まつり会館でお囃子の実演を行いました。以下フェイスブックより抜粋です。
当囃子連は日程に恵まれているのか、
今回の実演もに多くの来場者の前で
行うことが出来ました。
今回も実演後の撮影会は順番待ちが...
出るほど盛況でした。
そして、今回は当囃子連20年来の念願だった
浴衣の初披露でした。
これからは季節によって、お馴染み今成の着物と
この度新調した浴衣を使い分けていきます。
ご来場ありがとうございました。
次回は、実演は7月31日の百万灯夏まつりで
ご来場お待ちしております。